学術コンテンツの著作権の
お悩みはお任せください
「取りたいけど取り方がわからない」
「必要かどうかがわからない」
そんな時はナレッジワイヤへご相談ください
豊富な実績と経験で、その疑問にお答えします。
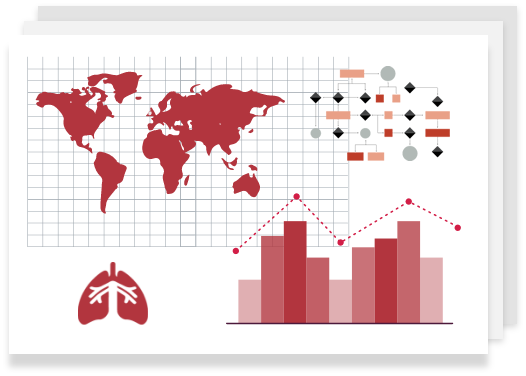

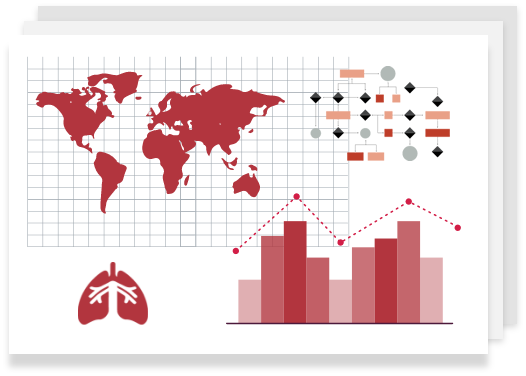
図表、写真、文章の転載で
こんなお悩みありませんか?

 投稿したら第三者の図表利用の許諾を取れと言われた。
投稿したら第三者の図表利用の許諾を取れと言われた。
今まで言われたことはなかったのに、どういうこと? 入稿直前になって転載許諾を取っていなかったことに気が付いた。
入稿直前になって転載許諾を取っていなかったことに気が付いた。
今からどうすればよい? 著作権処理費用まで十分な予算がない。
著作権処理費用まで十分な予算がない。
トラブルのリスクがないように制作するにはどうすればよい? 以前に許諾を取ったと聞いているが担当者もいなくて事情が分からない。
以前に許諾を取ったと聞いているが担当者もいなくて事情が分からない。
新たに別の資料にも使いたいが、取り直さないといけない? 最近、自社の出版物やWEBサイトからの転載許諾の依頼が来るようになった。
最近、自社の出版物やWEBサイトからの転載許諾の依頼が来るようになった。
どう対応してよいかわからない。
そのお悩み、解決します!
ナレッジワイヤなら
答えが見つかります
利用許諾を取る必要があるかどうか? どういう使い方なら許可されるのか?
費用はどのくらいかかるのか?
・・・皆様の様々な疑問やお悩みにも、
ナレッジワイヤなら適切なご回答が可能。
確かな実績をもとに、課題解決をサポートします。

医薬学術分野で
20年の実績
ナレッジワイヤは医薬学術分野に特化して20年の経験があり、著作権法についても、学術研究のマナーやルールについても熟知しています。例えば、どういう基準で許諾を取るか、取らなくても問題が起きないかなど、適切なご回答を致します。

客観的な根拠に
基づく
ご提案
ナレッジワイヤは国内外の学協会や出版社と常にコミュニケーションを取っています。権利者のポリシーを自己流に判断すると、後でトラブルになる可能性もあります。どういう使い方なら許可が出るのか、修正を指示される可能性があるのか、などナレッジワイヤしか知らない権利者の情報があります。

許諾料の予測金額まで
ご案内
利用者の立場で気になるのは利用時に発生する許諾料です。ナレッジワイヤは過去15年以上にわたって国内外のほとんどの学協会、出版社との実績があり、継続的に取引を行っています。最新の取引データをもとに、予想金額をお伝えすることが可能です。
ご相談は無料
ナレッジワイヤなら著作権法等の法律だけでなく、
学術コミュニケーションの慣行も踏まえて、
お答えすることができます。
ナレッジワイヤには
疑問を解決するノウハウがあります。
弊社の実績
知的財産管理技能検定・
ビジネス著作権検定等、
検定資格を有する
スタッフが相談に応じます。
取得した許諾総数
過去20年で
50000
以上
許諾を取得した海外権利者数
950
以上
許諾を取得した国内権利者数
250
以上
パートナー
出版社
当社はCopyright Clearance Centerの正規Business Partnerです
1万パートナー出版社数
以上
国内のお取引数
100
以上
※海外のお客様からのご利用もございます
納品までのながれ
1
利用予定図版等のご提示
出典資料と使用される図表数、制作物の概略、
部数等をお知らせください。
2
概算見積りのご連絡
弊社の過去実績データから
概算のお見積りをご連絡します。
3
作業開始のご指示
概算見積りを目安に具体的な図表や部数が確定しましたら、作業開始をご指示ください。出典資料コピー、
制作物見本、弊社所定「ご依頼内容確認シート」の
3点がそろえば作業がスムーズに運びます。
4
権利者からの回答
出版社・学協会等の権利者から
費用や条件の提示があります。
5
権利者条件等の承認又はキャンセル
許諾取得の最終指示を行います。
6
費用支払い・作業報告書の納品
弊社で権利者への支払い処理をおこない、
ライセンス書類などの成果物を納品します。
よくあるご質問
Q
政府刊行物は勝手に使っても問題ありませんか?
A
近年「オープンデータ」政策の推進により、政府機関の情報利用について、許諾なしに自由に使えるようにしていこうという流れがあります。2016年1月からは、Creative CommonsのCC-BYに準拠した「政府標準利用規約(第2.0版)」が政府機関の発信する情報には適用されます。これは出典さえ適切に書けば自由に使ってよく改変も自由というものです。そもそも従来も著作権法第32条に当てはまる場合は、許諾なしに利用することができましたが、現時点ではかなり広範囲に自由に使えるようになった、ということは言えます。
とはいえ、実務的には政府機関以外が著作権を持っているものが混在していることもあるため、慎重に内容を確認して使うことをお勧めします。
米国のCDCなどの刊行物については、連邦政府の職員による著作物はPublic Domainであるという規定がありますが、やはり第三者の著作物が紛れ込んでいないかの確認は必要です。
Q
イントラネットにアップする資料ですが、許諾を取らねばなりませんか?
A
外部に公開されないとしても、私的に使うのではない以上、著作物の利用には変わりありません。許諾を取って使う必要があります。
イントラネットに限らず、サーバからの配信は公衆送信権の問題になります。原則としてコンテンツを搭載するサーバごとに許諾が必要ですので、権利者に適切に通知する必要があります。複数のサイトで同じコンテンツを公開するような場合は、包括的な許可を明示的にとることをお勧めします。
Q
「名言」「格言」は自由に使えますか?
A
「名言」「格言」と言われているものは、形式的には、1-2文程度以内の短い文章、という事ができると思います。また、その文章を残した人は、既に亡くなっている場合と、現在も活躍している人の両方のケースがあると思います。 まず、著作権の保護期間は著作者が亡くなってから70年間ですから、保護期間が過ぎていれば気にすることはありません。保護期間が存続している場合は、その「名言」「格言」が「著作物かどうか」で判断することになります。短い文章だから「著作物」ではない、とも言い切れないため、この判断は難しいものです。
多くの場合は、著作権法上の「引用」規定で済むケースかと思いますが、「引用」規定に合わない場合でも、悪意を持った使い方や、名言を残された方にタダ乗りするような使い方でない限りトラブルになるケースは少ないでしょう。
もちろん、リスクを徹底的に回避するなら、その言葉を残した人またはその著作権の相続人に断りを入れることになります。
Q
「作図」と「改変」の違いは?
A
「~より作成、~より作図」の言葉は、オリジナルの資料にはないものを独自に作った、ということを指す場合に使い、「~より改変」は、オリジナルの資料を変更して使っている場合に記載することをお勧めします。 「作図」という言葉が「出典元にはないものをオリジナルに作った」という意味であれば、当然に出典元の権利者に許可を得る必要はありません。オリジナルの表現に準拠して部分的に変更した場合は、著作権法上の「翻案権」や「同一性保持権」に抵触する可能性があり、その場合は許諾が必要か、不要かの線引きはグレーです。
判例では「翻案権」の基準について、オリジナルの表現の特徴を感得できるかどうか、と言われています。感得できるなら翻案であり、感得できないほどオリジナルとは異なるなら、独自の著作物であるということです。
また、医薬理工系文献の領域=科学コミュニケーションの立場で考えると、当然ながら「内容」が変わっていることがより大きな問題です。これを著作権法の同一性保持権の問題と考えるかどうかは難しいところですが、実務的には、見た目がどうであろうと内容が変わっていなければ、元の著作者は気にしないことも多いですし、内容を変えるのであれば、見た目がどうであれ、何らかの了解が必要と考えるでしょう。
いずれにせよ、完全にオリジナルと言い切れるような作図にするか、あるいは、元の表現に準拠する場合は表現も内容もできるだけ元のままで使って許諾を取る、ということが許諾の交渉をスムーズに運ぶコツです。
Q
医薬・理工系の学術論文におけるグラフや表は許諾が必要ですか?
A
自然科学の学術論文中に現れる単純なグラフや表は、著作権法上では「著作物ではない」場合も多いと考えられますが、自然科学におけるグラフや表の意味は通常の図形とは異なるため、著作権法を越えて、慎重な取り扱いが必要です。
海外の理工系の出版社は、「いかなる部分でも無断で使ってはならない」、あるいは「フェアユースの範囲を超えて使ってはならない」と注意書きをするところが多くあります。米国で発行されている有名な論文の書き方、 Chicago Manual of Styleにしても医学系のAMA Manual of Styleを見ても、他人の図や表を使う際には許諾を取れ、と出てきます。理工系論文における図表はそれ自体で論文の主要な内容を表していることが少なくないからです。ある調査では理工系研究者にとって「図表」=図、写真、グラフ、表、を利用することは特別視されているという結果(注1)がでています。そこには著作権法上の問題とは別に、他人のデータを無断で使ってはいけないという研究倫理の問題が混じっていると思われますが、学術コミュニティと共同で研究やビジネスをおこなっていく場合は、そうした事情も無視することはできません。
注1) 青木早苗、杉村晃一「引用に関する調査-知的財産の保護と活用のために-」、メディア教育開発センター研究報告第47号、2004、p.15
Q
論文中に掲載されている写真の著作権の扱いはどうなっているのですか?
A
著作権法的には、一般的には平面のものを平面的に撮ったものは複製であって、立体物を撮った場合は写真の著作物=写真家の著作物であると言われています。
例えば、画家が亡くなって70年以上経過している有名絵画であれば、絵画自体の著作権も消滅していますし、それを画集に掲載するような複製として撮ったものは写真家の著作権も働きません。絵画を所蔵している美術館にお断りを入れる必要もありません。
一方、立体物の写真は撮る際に写真家の個性や創作性が入り込む余地があり、写真の著作物と認められることが多いようです。しかし顕微鏡の写真、CTやMRIの写真、超音波の写真などはどうか、悩ましいところです。創作性が入り込む余地が全くないとは言えないように思います。また著作権の問題ではないですが、その写真に撮られている患者さんのプライバシーはどうなのか、ということも気になります。実務的には論文の中の写真を使いたいという場合は、やはり出版社や著者に連絡をすべきだろうと思います。ただし論文に掲載の写真は、しばしば著者がほかの研究者から提供を受けているケースもあります。その様な場合は、提供元の研究者に連絡をする必要があります。
Q
複数の著者がいる場合、誰に連絡すればよいですか?
A
Corresponding author、Contact author、別刷り請求先、連絡先、等として記載されている人に、まず連絡します。出版社に権利が譲渡されていれば、出版社から許諾を取れば良いのですが、著者から許諾を得なければいけない場合もあります。わが国の著作権法では、共著、つまり共同著作物の権利行使には、著作者全員の許諾が必要というのが原則です(第64条、65条)が、「共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる(第64条)」という条項があり、この規定は第65条で「共有著作権の行使にも準用する」とあります。一般的に、Corresponding author、Contact author、別刷り請求先、連絡先、等として記載されている人が、「代表して行使する者」に当たると考えられます。また「Corresponding author とは連絡係のように聞こえるが、実際には、論文の全責任を負う著者のことである」(注1)とあるように、「責任著者」です。
一方、米国著作権法では、通常の転載許諾のケースのような「非独占的許諾」、つまり独占契約ではない利用許諾は、共同著者の一人が単独で行使できることになっています(注2)。従ってこちらは著者許諾が必要な場合、誰か一人から許諾をとっていれば十分ということになります。
注1) 黒木登志夫「研究不正」、中公新書、2016、p.155-156
注2) 山本隆司「アメリカ著作権法の基礎知識」第二版、太田出版、2008、p.75
Q
以前製作した資材の増刷やWEB掲載には再度許諾が必要ですか?
A
以前の利用許諾でカバーされている範囲かどうかが問題です。
通常はOne Time、その時限りの許諾が多いため、増刷の場合やメディアを変える場合、別の資材へ使う場合などは再度許諾が必要なことがほとんどです。
著作権法第63条2項
その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる
許諾はあくまで、「許諾申請した内容」に限っているので、申請していない使い方(部数も含め)はできません。ですから、実際の印刷は分割して行うとしても、おなじ権利を取る場合で最終的な部数が最初からわかっていれば、最初からその部数を申請するほうが手間も費用もかかりません。
Q
社内利用の資料ですが、許諾が必要ですか?
A
社内で閲覧する資料、研修料資料であっても、自らに著作権のない資料を利用するには許諾が必要です。
著作権法では「私的利用」は許諾なしにおこなうことが認められていますが、「私的利用」とは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(第30条)」とされており、「特定かつ少数」と言われることもあります。企業で利用する場合は、社内利用であっても、これには当てはまりません。
「研修用」であるかとか、「外部へ頒布しない」といったことが、よく無断で利用する場合の理由に挙げられますが、残念ながら著作権法はそのような理由は認めておりません。もちろん権利者側が外部への頒布の有無や配布部数などを許諾条件の中で考慮する場合はあります。業務上で利用する場合は「個人的」であっても「私的」とはイコールではないことに注意が必要です。
Q
転載しようとした図表に別の資料の出典が記載されていました。どうすればよいですか?
A
大元の出典にあたり、確認するのが原則です。その上で、必要に応じてどちらか一方か、あるいは両方から許諾を取る必要があるかどうかを判断し、また出典の表記も両方を併記するか、片方だけにするかを決めます。
いわゆる孫引きのケースです。作成しているものをAとします。そこに、Bからの図表を転載しようとしたら、Bは実はCからの転載、またはCをもとに作成されたものであったというケースです。この時AはCの孫引きとしてBを使った、ということになります。理工系文献では過去の研究データの上にデータを追加して研究の積み重ねが行われるため、こうした事例も少なくありません。
このような事例において、転載許諾を取るという観点からは次のように二つのケースに分かれます。
(1)C(元のデータ)→B(独自に作成した図表など)→A(自分の原稿)
この場合、著作権法上ではAはBから許諾を取ればOKです。Cの著作物をBは使っていないからです。ただし、学術情報の領域では、Bだけでなく、「Data from XXX」などと、元データの出典も書くことが推奨されます。許諾を取ったことと、出典を書く書かないは別です。またBの図表にデータの出所としてCが記載されているのに、それをわざわざ消すのか、ということにもなります。「データはXXXから」と書いてあれば当然それも一緒に写すべきでしょう。
(2)C(著作物とみなせる図表など)→B(それを元にした図表など)→A(自分の原稿)
この場合はBとCの両方から許諾が必要です。BはCから派生した二次的著作物であり、その場合には原著作物(C)の許諾も必要、というのが著作権法のルールです。出典も両方書くべきです。
ただし、自分の原稿が、Cを利用したとも、Bを利用したともいえる場合は、どちらにより近いか、で判断します。できれば大元のオリジナルからのほうが良いので、CをもとにしてCから許諾を取るのが良いと思いますが、Bを使いたい、ということであれば、上述したように、BとCの両方の許諾が必要になります。
いずれにせよ、利用しようと思っている図表の下にオリジナルの出典が記載されていないか、あるいは参考文献番号が振られていないか、などは図表利用の際には必ずチェックする必要があります。
Q
大学の業績集に所属教員の発表論文の全文を転載したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A
研究業績をまとめて「年報」として発行したり、記念論文集などとして出版したりすることがあります。
書き下ろしの論文や記事であれば、著作権法上の許諾等の問題はありませんが、医学系などでは、学術誌に掲載された論文を部門の実績として転載するというケースがあります。当社でも何度もそうしたケースのお手伝いをさせていただいています。学術誌に掲載された論文をそのまま全文転載したり、抄録だけを転載したり、論文の一部分だけを転載するなどの場合は、著作権者に許諾が必要な場合がほとんどです。
無償で頒布するからといって、なにもしないのは不適切です。とはいえ、論文や雑誌によっては営利目的でなければ自由に使ってよい=複製・転載してよい、というものもありますので、この辺りの確認が最初の作業となります。
Q
引用とは何ですか?
A
一般に第三者の文章や図表などを利用する事を「引用」と言いますが、著作権法上では「引用」とは以下のように書かれています。
著作権法第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない
つまり、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」を引用と言います。また関連して第48条では出所の明示を義務付けています。従って、これらの要件に当てはまる場合は、著作権者に断ることなく利用しても構わない、ということになります。条文が要件としてあげている「公正な慣行」と「正当な範囲内」については、これまでの判例から「著作物全体の中で、引用部分は主従関係の従たる扱い」「引用箇所の明瞭区分性」「必要最小限」などが言われています。しかし「報道、批評、研究その他の引用の目的」と書かれた部分をどう解釈するかは様々な意見があります。とはいえ、製品情報パンフレットのような明らかな広告が、報道、批評、研究その他の目的、に同列で列挙されうると考えるのは、抵抗があると思います。広告中で掲載されるということは、その広告が対象としている製品やサービスを提供している企業の営利活動に協力する、ということであって、これが無断でおこなわれてもよい、というのは想定しづらいでしょう。また、論文紹介パンフなどは大方の意見の一致をみている「主従関係」や「明瞭区分性」の観点からも当てはまらないと言えますので、プロモーション関係での利用の場合、著作権法の「引用」の規定を当てはめるのは難しいように思います。
企業情報
| 社名 | 株式会社ナレッジワイヤ KnowledgeWire Corp. |
|---|---|
| 本社所在地 | 160-0022 東京都新宿区新宿1-3-8 YKB新宿御苑ビル 503 |
| 設立 | 2000年6月1日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表取締役社長 | 伊藤 勝 |
| サイトURL | https://www.kwire.co.jp/ |
| 加盟学協会・団体 (法人・個人) |
著作権法学会会員 公益社団法人著作権情報センター賛助会員 日本ユニ著作権センター正会員 |
| 資格(代表者・スタッフ) | 行政書士・著作権相談員 知的財産管理技能士2級 ビジネス実務法務検定準1級・2級 ビジネス著作権検定上級 薬学検定1級 登録販売者試験合格者 検索技術者検定1級 |
| その他 | 米国 Copyright Clearance Center 正規パートナー |
| 認証 | ISMS認証:登録番号IC21J0529 規格ISO/IEC27001 |

